|
|
| TOP>生産者一覧>ひもの釜鶴 |
 |
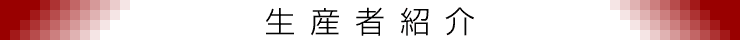 |
 |
| 表の見方 |
 |
 所在地
所在地  名前
名前  店舗名
店舗名  職業
職業  おすすめ商品
おすすめ商品  生年月日
生年月日  星座
星座  座右の銘
座右の銘 |
|
|
 |
 |
 |
静岡県 |
 |
二見一輝瑠さん |
 |
ひもの釜鶴 |
 |
ひもの釜鶴 五代目 |
 |
金目鯛、アジ |
 |
1978/08/29 |
 |
おとめ座 |
 |
歴史の重みを感じながら作っています。 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
釜鶴さんの干物作りのこだわりは何ですか?
「まず、減塩であるということ。それから素材にこだわっていて、生の地物を中心に製造しています。」(四代目・二見康一さん)とのこと。
釜鶴さんの答えは明快です。刺身でも食べられるような、その日に獲れた一番良い魚を吟味して干物を作ってらっしゃるそうで、干物への自信がキッパリと現れています。
作り方にもいろいろ心を砕いてらっしゃるとか。
「水は精製水にして(魚を洗うのに)使っています」し、「駿河湾の深層水を混ぜて(荒塩を使った)塩ダレを使っています。」(同)とのこと。また、魚をさばいて加工する作業所が非常に清潔なのが印象的でした。
よそにはない釜鶴さんの特徴ってありますか?
「魚種が多いです。アジだけでも6種類、7種類。小魚も高級魚も。甘鯛、アオリイカ、柳ガレイ。伊勢エビなんかも作ります。」(同)
昨今はお客さんの好みに合わせて塩分は徐々に控えめになっているそうですが、それ以外は、「市内で自家製で、職人さんが作っているところはウチぐらいのもん」だそうで、昔ながらの無添加の製法をかたくなに守って作り続けているいるそうです。
築地でも修行されていたという五代目の二見一輝瑠さんは、干物作りの現場を案内してくださりながら、「干すのは風が重要なんですよ。」とおっしゃいました。その時の熱海の海と空がなかなかきれいだったのが印象的です。 |
|
|
ご先祖様の心意気を胸に。
釜鶴さんのご先祖様、釜鳴屋平七は江戸時代の網元でした。
ところが、安西四年(1857年)、網元と漁民の間に争いがおこり、網元であるにもかかわらず、重税に苦しむ漁民のために当時の代官に直訴したところ、首謀者として捕らえられ、五年間の入牢の末、八丈遠島の途中、伊豆大島で亡くなってしまいました。
しかし、その甲斐あって、13年に渡る対立の末、漁民に有利に事件は解決されたのです。その釜鳴屋平七の三男、鶴吉さんが釜鶴さんをはじめました。
五代目の二見一輝瑠さんは、干物作りの上で一番気に掛けていることを、「歴史の重み」とおっしゃいました。
「五代目と言っても、日本中ではそんなに長くないと言われてしまうかもしれませんけれど、先代までずっと続けてきたものを守りながら、新しいものを作っていくという重みはあります。」
きっと、二見さんの心には、ご先祖様の釜鳴屋平七の心意気が生きているのでしょう。 |
|
|
| |
| ©
copyright 2004 匠の箱 All Rights Reserved. |
|